セイタカアワダチソウの可能性
皆さん、こんにちは!
冬の野草生活を楽しんでいますか?
まだまだ青々とした野草を見つけることができますが、「枯れ草ばかりで野草生活はできないなあ」と思っている方がいれば、こちらの記事もチェックいただければ幸いです♪
▶︎▷▶︎ 枯れ草を活かす【冬の野草の魅力】(小釣はるよ Ameba blog)
さて、今日はコチラの野草について書きたいと思います!

そう!
セイタカアワダチソウです!
皆さんはセイタカアワダチソウについてどんな印象をお持ちですか?
以前書かせていただいたセンダングサと同じく、このセイタカアワダチソウも結構な嫌われ者で、「セイタカアワダチソウ」と検索すると、【駆除・外来種・アレルギー】などといったような予測キーワードが並び、邪魔者扱いを受けていることがわかります。
まず一つ大きな誤解を解いておきたいのですが、、、
花粉症の原因だとされていますが、セイタカアワダチソウは虫が花粉を運ぶ「虫媒花」なので、花粉症の原因ではないとされています。
(セイタカアワダチソウの花粉は重くて風で運ばれることはないそうです!)
花粉症の原因の正体は「ブタクサ」なのですが、この二つの野草はよく似ていて、また同じ時期に大繁殖したことから、犯人扱いを受けていたんですね。(後ほど見分け方も記述します!)
サラッと一つ誤解を解いたところで、今回は「セイタカアワダチソウ」ってすごいじゃん!と思っていただけるような記事を書いていきたいと思います。(ブタクサも実はすごいですよ!!!)
セイタカアワダチソウって
どんな野草?
原産は北アメリカで、観賞用・蜜源植物として明治30年頃に日本に入ってきて、現在では雑草化して河川敷や空き地などでよく見られる野草です。
開花時期は10月~11月とされていますが、最近では12月に入ってもよく見かけるようになりました。

<セイタカアワダチソウ>
キク科アキノキリンソウ属
学名:Solidago altissima
※Solidago:アキノキリンソウ属 / altissima:非常に丈の高い
Solidago(ソリダーゴ)は、ラテン語の「solidus(完全な)+ ago(導く)」が語源となっており、古くは傷薬として使用されていたことからこの学名が付けられたそうです。
ブタクサとの違い

※画像引用(右):セイタカアワダチソウとブタクサの違いや駆除方法は?花粉症の原因はどっち?アレルギー対策の仕方まで現役薬剤師がわかりやすく解説
ブタクサは、キク科ブタクサ属の一年草です。
数ミリの黄色い小花がつきますが、遠目には見えづらく花穂は緑色に見えます。
ブタクサの葉は細く切れ込んで分裂し、ヨモギに似た形をしています。(画像:右)
上の写真で分かるように、セイタカアワダチソウの葉は細長く、切れ込みがなくすっきりしています。
対してブタクサの葉は切れ込みがあり広がっています。
葉の形状が見分けるポイントですね!
ブタクサは、風で花粉を飛ばして受粉させる「風媒花」であるため、花粉が大量に飛散します。
そのため、人が吸い込んでしまい花粉症の原因となります。
【ブタクサの効果効能】
ブタクサの印象が悪くなってしまうといけないので、ここでブタクサの薬効を書かせていただきますね。
ブタクサには多くの薬効があると言われています。
ブタクサは主に【収れん剤、防腐剤、催吐剤、皮膚軟化剤、解熱剤】という目的で使われていました。
主な活用例をこちらに記載しますね。
<<お茶として>>
アメリカ先住民の一部の部族では、ブタクサの根でお茶を作り、下剤として活用していたそうです。
ブタクサのお茶は、発熱、吐き気、赤痢、鼻血の治療に使用されていました。
一部のネイティブ アメリカンは、ブタクサのお茶で脳卒中を治療したとの記載も見られます。
<<葉をすり潰して>>
ブタクサの葉を砕いて、小さな傷にこすりつけて出血を止めたり、虫刺され、ハチ刺され、かぶれ、蕁麻疹のかゆみ止めに使用されていたそうです。
ブタクサの花粉は、花粉症の自然療法に使用されることがあります。
<参考文献>
○RAGWEED: THIS FOE MAY BE A FRIEND TOO by Jonah Holland
○Ragweed considered pest, but offers medicinal purpose
次に「セイタカアワダチソウ」の効果効能をご紹介していきたいと思います。
セイタカアワダチソウの効果効能
<<含まれる成分>>
タンニン、トリテルペノイド サポニン、フラボノイド (ルチンとケルシチン)、フェノール酸、多糖類、サリチル酸塩 etc…
セイタカアワダチソウは、古代ローマ時代から薬効があると考えられていました。
主に【駆風剤、興奮剤、収斂剤、発汗剤、強壮剤、利尿剤、抗炎症剤、抗菌剤、鎮痛剤】として利用されていました。
セイタカアワダチソウも、北米の先住民によって多くの病気の治療に使用されてきた歴史を持ちます。
根っこで作ったお茶は神経痛に利用され、また根っこ自体は口の痛みのために噛んだり、歯痛のために使われていたそうです。
葉っぱで作ったお茶は、結核の治療に使われていたとの記述が見られます。
セイタカアワダチソウの仲間たち
「セイタカアワダチソウ」は、”アキノキリンソウ属”の野草ですが、原産地のアメリカでは、この「アキノキリンソウ」を薬用する文化があったそうです。
今日では、アキノキリンソウ(属)は尿路感染症や膀胱感染症の治療薬としてよく知られており、腎臓のバランスを回復する利尿薬としての役割を果たしています。
また、抗菌性のハーブとして、風邪や喉の痛みの治療に使用することができます。

(画像:アキノキリンソウ)
アキノキリンソウには、天然の抗ヒスタミン剤であるケルセチンとルチンが含まれており、季節性アレルギーの緩和に使用することができます。
主に、痛みや腫れ(炎症)を軽減し、利尿剤として利尿を促し、筋肉の痙攣を止めるために使用されます。
また、痛風、関節痛(リウマチ)、関節炎、湿疹やその他の皮膚症状にも使用されます。
<参考文献>
○YAHOLA HERBAL SCHOOL:Goldenrod (Solidago) a powerful medicinal herb!
○VITAMINS, HERBS, AND DIETARY SUPPLEMENTS:GOLDENROD
※注意点※
①妊娠中(または授乳中)の使用について
妊娠中または授乳中の場合、セイタカアワダチソウ(アキノキリンソウ属)を服用することの安全性に関する信頼できる十分な情報はありません。
②ブタクサおよび関連植物に対するアレルギー
セイタカアワダチソウ(アキノキリンソウ属)は、「キク科の植物」に敏感な人にアレルギー反応を引き起こす可能性があります。
※使用するのが不安な場合は、パッチテストの反応を見てからの使用をおすすめします。
セイタカアワダチソウの活用術
民間療法では「お茶」が定番ですが、特におすすめしたいのは「薬湯」です!

セイタカアワダチソウの薬湯は、「発汗性」が凄いです!
私は、薬湯を入れると、三日間くらいは追い焚きして同じお湯でお風呂に入ります。
そうすると、お風呂のお湯が発酵してきて、発汗性も高まりますし、お風呂上がりのお肌のスベスベ感が感動ものなので、是非お試しいただきたいです♪
★薬湯の作り方★
薬湯の作り方とお茶の作り方は同じだと思っていただいても大丈夫です。
- 摘んできた野草を乾燥させる。
- 土鍋で炒る。
この2工程で完成ですが、完璧を目指される方は、ミキサーや粉砕機を使って細かくしてください。
一度にたくさんできるので、できた薬湯はティーバッグに入れて小分けにしておくと、扱いやすくて便利です。

ちなみに、、、
私は、摘んできたセイタカアワダチソウを他の野草と一緒に洗濯ネットに入れて、そのままお風呂に入れておくという、超ズボラな方法でセイタカアワダチソウの薬湯風呂を楽しんでいます^^
★フレッシュハーブティー★
次におすすめしたいのは、セイタカアワダチソウのフレッシュハーブティーです!
摘んできた野草を耐熱ポットに入れて、そこにお湯を注げば完成です!

セイタカアワダチソウの生命力をダイレクトに感じられるので、こちらも超おすすめです!
解毒効果が高く、「お茶」や「薬湯」としてセイタカアワダチソウを活用することで、アトピー性皮膚炎が改善された事例がたくさん上がっています。
また、炎症を緩和する抗菌・抗炎症作用があるので、口内炎ができた時などは、セイタカアワダチソウのお茶をうがい薬として活用しています。
セイタカアワダチソウを食べる!
ここまでは一般的ですが、E&Wラボではこのセイタカアワダチソウを野草料理にも活用します!
今まで作ってきた野草料理だと
- セイタカアワダチソウのスコーン
- セイタカアワダチソウのシチュー
- セイタカアワダチソウの蜂蜜ジャム
- セイタカアワダチソウのペペロンチーノ
- セイタカアワダチソウの糠漬け
などなど、秋から冬にかけての旬の野草として、積極的に活用しています^^
セイタカアワダチソウってお茶にして飲んでも、食べても、とても苦いです。
ですので、一般的に食用ではおすすめされていませんが、私たちは敢えてこの野草の苦味を生活かします!
私の感覚ですが、セイタカアワダチソウの苦味は、お花と葉っぱでは少しだけ違いがあるような感じがします。
お花は蜜があるので、苦味の奥の方にかすかな甘味があるような感じです。
葉っぱは、ハーブのようなスッキリとした薬草としての苦味があります。
この苦味をお料理に活かすには、多めのオリーブオイルとニンニクと一緒に低温でじっくり炒めることがポイントです。
そうすることで旨味を感じる苦味になります!

お菓子に使う時は、少量にするのがポイントです。
ハチミツ漬けや糠漬けは、熟成させることで苦味がまろやかになり、苦味を旨味として感じられるようになります
(そこまでして使う!?という意見もありますが。笑)

野草の苦味は、慣れてくると不思議と美味しく感じてくるんです。
子どもの頃は苦味を美味しく感じないけど、大人になるとビールやブラックコーヒーの苦味が美味しく感じるという感覚と似ている気がします。
必要だからそこに在る
人とのご縁があるように、野草とのご縁もあると、私は思っています。
セイタカアワダチソウが持つ、「アレロパシー」という成分は、他の植物の成長を妨げるとされ、セイタカアワダチソウは環境省が定める「生態系被害防止外来種リスト」に掲載されています。
この成分によって、自分自身も枯らしてしまうことがあるそうです。
これってすごいことじゃないですか?
これは私の勝手な主観ですが、
セイタカアワダチソウは分かっていて自分自身を枯らしていると思うんです。
野草は土壌環境のバランスと大きく関わり合っています。
例えば、ミネラルが不足する土地にはスギナが沢山生え、土壌のバランスが整うと、それからは生えなくなっていきます。
セイタカアワダチソウを含めて、すべての自然物には無駄がないと思っています。
必要だからそこに在る。
自然が出した“必要性”という問いかけに、私たち人間がどう答えを出していくか?がこれから先の未来を決めると思います。
「除草剤を使って駆除する」
「そのまま放置し続ける」
「お茶や薬湯にして楽しむ」
どれも、“人間が出した1つの答え”という次元では同じです。
それぞれの立場、環境、それからタイミングによって、何が正解になるかはわかりません。
その瞬間瞬間で最も心地よいと思える選択をし、答えを出していくこと。
それが最善であり、最も美しい答えだと思います。
この記事を読んでくださっている方々に、心地よい選択をしていっていただくためにも、これからも私なりに出した答えを発信していきたいと思います^^

「セイタカアワダチソウ」
「ブタクサ」「アキノキリンソウ(属)」
ある日この野草と目が合ったら、是非活用してみてくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
野草の可能性は無限大
E&Wラボでは、今すぐ実践できる「野草生活のノウハウ」を学んでいただける、
毎月2度の1DAYオンライン講座を開講しております。
▲いろんな健康法を試してきたけど、
どれも効果がイマイチで・・・
▲体だけでなく心の部分も癒していきたい
▲自然のリズムで日々を心地よく過ごしていきたい
という方には、
「野草と発酵を取り入れた究極のオーガニックライフ」が超おすすめです!
長年学んで来られた健康法の知識も活かしつつ、
そこに野草と発酵の要素が加われば、
これほど強いものはありません。
1DAYオンライン講座では、
「今オススメしたい旬の野草」
「秘められた野草の可能性や魅力」
「今の自分に必要な野草の選び方」
「潜在意識を癒す野草のメッセージ」
などをお伝えさせていただきます。
2025年8月の日程はこちらです。
※定員がございますので、ピンと来たかたはお早めにお申し込みください。
<開催日>
◆8月12日(火)13時〜17時
◆8月28日(木)13時〜17時
ピンと来た方は、ぜひ遊びに来てください^^
年間オンライン講座のご案内
E&Wラボでは、「野草と発酵ライフ」をオンライン上で学んでいただき、一年間で、それぞれの生活スタイルに合わせた「究極のオーガニックライフスタイル」を構築いただける、日本で唯一の「野草と発酵が学べるオンラインスクール」を運営しております。





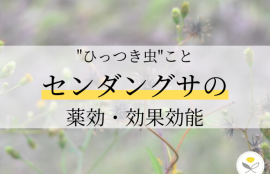
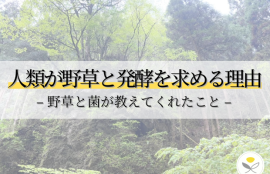

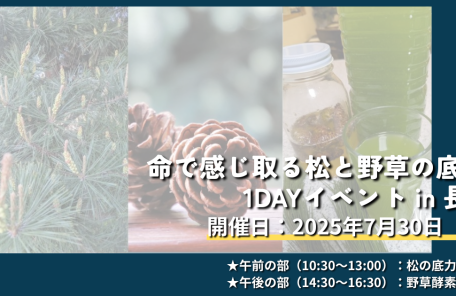
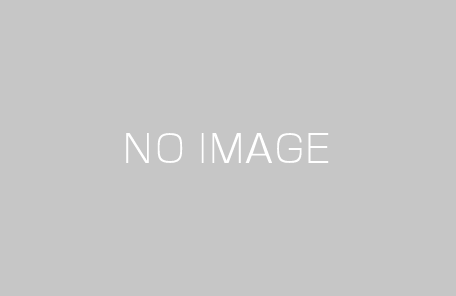


この記事へのコメントはありません。