春の野草シーズン到来
食べられるおすすめの春の野草をご紹介します。
薬効成分や効果効能、また調理法の例をまとめたので、これらを参考にこれから始まる野草シーズンをお楽しみいただけたら幸いです!
食べられる【春の野草20選】※五十音順
イヌガラシ

- 薬効成分/効果効能: ビタミンC、β-カロテン、ミネラル / 食欲増進、抗菌、抗炎症作用
- おすすめの調理法: 若葉をサラダ・おひたし・和え物、薬味
- 採取できる場所: 畑、道端、荒れ地
- 特徴と豆知識: アブラナ科の一年草で、春に黄色い小さな花を咲かせます。葉をもむとわずかに辛味のある香りがします。生命力が強く、様々な場所で生育します。名前の由来は、「犬」は接頭語的に使われ、役に立たない芥子という意味合いが含まれているとする説がありますが、実際には食用にでき、薬効もある有用な野草です。
オオバコ

- 薬効成分/効果効能: アウクビン、プランタギニン / 鎮咳、去痰、止血、抗菌作用、便秘解消
- おすすめの調理法: 若葉を茹でておひたし・和え物・炒め物、天ぷら・かき揚げ
- 採取できる場所: 道端、空き地、畑の畦道
- 特徴と豆知識: オオバコ科の多年草で、広い葉が特徴です。踏みつけに強く、道端などでもよく見られます。古くから傷薬や止血薬として利用されてきました。葉を揉んで傷口に当てると、止血や殺菌効果が期待できます。花は目立たない穂状で、風媒花です。「大葉子」の名前は、大きな葉を持つことに由来します。オオバコの種子は水を含むとゼラチン状になる性質があり、食物繊維が多く含まれているため、便秘解消に役立つとされています。
オランダミミナグサ

- 薬効成分/効果効能: ビタミンC、ミネラル / 利尿作用、消炎作用
- 調理法の例: 若葉をサラダ、おひたし、和え物、スープの浮き身
- 採取できる場所: 道端、庭、畑
- 特徴と豆知識: ナデシコ科の越年草で、ヨーロッパ原産の帰化植物です。白い小さな花が特徴で、花弁が深く2裂している様子がミミナグサ(耳菜草)に似ていることから名付けられました。繁殖力が強く、畑や庭にもよく侵入します。「オランダ」は、外国から来た植物であることを示す接頭語として使われています。ミミナグサの仲間は多数ありますが、オランダミミナグサは特に葉が大きく、繁殖力が強いです。柔らかい若葉は、サラダなどにして食べられます。
カキドオシ

- 薬効成分/効果効能: ビタミンC、ミネラル、精油成分 / 健胃、利尿、消炎作用、リラックス、抗菌作用
- 調理法の例: 若葉をサラダ・和え物・天ぷら、ハーブティー、肉料理の臭み消し
- 採取できる場所: 日当たりの良い草地、道端、庭
- 特徴と豆知識: シソ科のつる性の多年草で、茎が地面を這うように伸び、垣根などを通り抜けて繁茂することから名付けられました。葉をもむと清涼感のある香りがします。この香りは精油成分によるもので、リラックス効果や抗菌作用が期待できます。春に淡紫色の可愛らしい花を咲かせます。ハーブティーとして利用する場合、乾燥させた葉を使います。生葉を傷口に当てると、止血や消炎効果があるとも言われています。
カタバミ

- 薬効成分/効果効能: ビタミンC、シュウ酸、クエン酸 / 抗酸化作用、美肌効果
- 調理法の例: 葉をサラダ、刻んでドレッシング・ソース
- 採取できる場所: 道端、庭、畑
- 特徴と豆知識: カタバミ科の多年草で、ハート形の葉が3つ集まった独特の葉が特徴です。日当たりの良い場所では葉を広げ、日陰や夜間には葉を閉じる就眠運動を行います。黄色い小さな花を咲かせ、果実は熟すと弾けて種子を飛ばします。繁殖力が強く、一度生えると駆除が難しい雑草としても知られています。「傍食(かたばみ)」の名前は、葉が半分欠けたように見えることから、「片喰み(かたはみ)」が転じたとする説があります。葉にはシュウ酸が含まれているため、酸味があります。この酸味を活かして、レモンのように料理に使うこともできます。カタバミの家紋は有名で、武家の間で広く用いられました。
カラスノエンドウ

- 薬効成分/効果効能: ビタミンC、食物繊維、タンパク質 / 便秘解消、筋肉組織形成、利尿、むくみ解消
- 調理法の例: 若芽とツル先を軽く茹でて、おひたし、和え物、天ぷら、炒め物 (※ゴマ和えやマヨネーズ和えなど風味の強い調味料で和えるのがおすすめ)、チャイ
- 採取できる場所: 道端、空き地、畑
- 特徴と豆知識: マメ科の一年草で、春に紫色の小さな花を咲かせます。ツル性の植物で、他の植物や物に絡みつきながら生育します。若い果実はサヤエンドウに似ていますが、熟すと黒くなり、カラスのようであることから「カラスノエンドウ」と名付けられました。別名として「ヤハズエンドウ」とも呼ばれます。葉の先端が矢筈(やはず)のように凹んでいることに由来します。若い果実の中には、小さな豆が入っています。カラスノエンドウによく似たスズメノエンドウという野草もありますが、スズメノエンドウの方が全体的に小さく、花の色も薄紫色です。
ギシギシ (羊蹄)

- 薬効成分/効果効能: ビタミンC、鉄分、カリウム / 貧血予防、むくみ解消
- 調理法の例: 若葉を茹でてアク抜き後、おひたし・和え物・炒め物・煮物
- 採取できる場所: 道端、空き地、河原
- 特徴と豆知識: タデ科の多年草で、大きな葉と背の高い茎が特徴です。葉や茎を折ると、ねっとりとした液体が出てきます。果実が熟すと茶色くなり、風に揺れると「ギシギシ」と音を立てることから名付けられました。繁殖力が強く、畑の雑草としても厄介者扱いされることがあります。「羊蹄(ようてい)」は漢名で、葉の形が羊の蹄(ひづめ)に似ていることに由来するとされます。
※若い葉は食用になりますが、シュウ酸を多く含むため、アク抜きされることを推奨します。
シロツメクサ

- 薬効成分/効果効能: ビタミンC、ミネラル、イソフラボン / 更年期症状緩和、止血、抗菌作用
- 調理法の例: 花と葉をサラダ・和え物・天ぷら、花をハーブティー、砂糖漬け、ジャム
- 採取できる場所: 草地、公園、道端
- 特徴と豆知識: マメ科の多年草で、クローバーとも呼ばれ、四つ葉のクローバーを探す遊びでおなじみです。白い球形の花が特徴で、蜜源植物としても重要です。明治時代にオランダからガラス製品の梱包材として日本に持ち込まれました。梱包材として詰め物に使われたことから「詰草(ツメクサ)」と名付けられました。白い花なので「白詰草」です。繁殖力が強く、グラウンドカバーなどにも利用されます。四つ葉のクローバーは、突然変異で生じると考えられており、幸運の象徴とされています。花を乾燥させてハーブティーにすると、ほんのり甘い香りが楽しめます。
スイバ

- 薬効成分/効果効能: ビタミンC、シュウ酸 / 疲労回復、食欲増進 (※シュウ酸を含むため、アク抜きと少量摂取が推奨されます)
- 調理法の例: 若葉を茹でておひたし、和え物、炒め物、スープ (※アク抜きはしっかりと)
- 採取できる場所: 道端、草地、畑
- 特徴と豆知識: タデ科の多年草で、赤みを帯びた茎と、酸味のある葉が特徴です。この酸味から、「酸葉(すいば)」と名付けられました。別名「スカンポ」とも呼ばれます。春から夏にかけて、穂状の赤い花を咲かせます。葉の酸味はシュウ酸によるものです。
スギナ

- 薬効成分/効果効能: ケイ素、ミネラル、カルシウム / 利尿作用、デトックス効果、美肌効果
- 調理法の例: 若芽(ツクシ)を卵とじ、和え物、佃煮、炒め物、乾燥させてお茶・ふりかけ
- 採取できる場所: 土手、道端、湿った場所
- 特徴と豆知識: シダ植物の一種で、ツクシ(土筆)としてよく知られる胞子茎と、緑色の栄養茎(スギナ)の2種類の茎を持つ植物です。ツクシは春の訪れを告げる野草として親しまれています。スギナは、地下茎を伸ばして繁殖するため、一度生えると駆除が難しい雑草としても知られています。ツクシはスギナの胞子茎で、春にニョキニョキと顔を出します。スギナは乾燥させてスギナ茶として飲んだり、煎ってふりかけにすることができます。ケイ素を豊富に含み、美容や健康に良いとされています。スギナはホウレンソウの約155倍ものカルシウムを含むとされています。研磨作用があるため、昔はスギナで鍋などを磨いたそうです。
スミレ

- 薬効成分/効果効能: ビタミンC、ルチン / 毛細血管強化、高血圧予防、抗炎症、抗酸化作用
- 調理法の例: 花と葉をサラダ、花の砂糖漬け、葉を天ぷら・おひたし・和え物
- 採取できる場所: 日当たりの良い草地、道端、公園
- 特徴と豆知識: スミレ科の多年草で、紫色の可愛らしい花が春の野原を彩ります。花の色や形、葉の形など、種類が非常に豊富です。名前の由来は、花の色が墨入れに使われた墨の色に似ているとか、花が「墨入れ」という道具に似ているなど、諸説あります。控えめな美しさから、古くから日本人に愛されてきた野草です。スミレの花言葉は「謙虚」「誠実」「小さな幸せ」など、スミレのイメージに合ったものが多くあります。
タンポポ

- 薬効成分/効果効能: タラキサシン (苦味成分)、イヌリン、カリウム、ビタミンC、β-カロテン / 胆汁分泌促進、消化促進、利尿、便秘解消、抗酸化作用、免疫力向上
- 調理法の例: 若葉をサラダ・おひたし・炒め物・天ぷら、根をタンポポコーヒーに、花をサラダ・天ぷら・ハーブティー
- 採取できる場所: 道端、空き地、公園
- 特徴と豆知識: キク科の多年草で、黄色い花と綿毛のついた種子が特徴です。生命力が強く、アスファルトの隙間など、厳しい環境でも生育できます。種子が風に乗って遠くまで運ばれることから、繁殖範囲が広いです。根は太く、タンポポコーヒーの原料として利用されます。ノンカフェインで、独特の香ばしい風味が楽しめます。セイヨウタンポポと在来種のタンポポがあり、総苞外片の反り返り方で見分けることができます。
ドクダミ

- 薬効成分/効果効能: クエルシトリン、精油成分 / 利尿、便秘解消、動脈硬化予防、抗菌・消臭作用
- 調理法・活用法の例: 若葉を天ぷら、乾燥させてドクダミ茶、お風呂に入れてドクダミ風呂、麻婆豆腐、チンキ、化粧水
- 採取できる場所: 半日陰の湿った場所、道端、庭
- 特徴と豆知識: ドクダミ科の多年草で、独特の強い臭いが特徴です。白い花びらのように見える部分は、実は萼(がく)で、中心にある黄色い部分が花です。繁殖力が非常に強く、地下茎を伸ばして広範囲に増え、一度生えると駆除が難しい厄介な雑草としても知られています。薬効成分が豊富で、生薬としても利用されます。名前の由来は、毒を矯(た)めるほど薬効があるという意味の「毒矯(ドクダメ)」が転じたとする説や、毒や痛みのある腫れ物「癪(しゃく)」に効くことから「癪草(シャクドメ)」が転じたとする説などがあります。独特の臭いは、乾燥させると気にならなくなります。ドクダミ茶は、ノンカフェインで、利尿作用や便秘解消効果が期待できます。ドクダミ風呂は、肌荒れやあせもなどに効果があると言われています。
★ドクダミ麻婆豆腐のレシピはこちら
ドクダミの自然の恵みを丸ごといただく。
ナズナ

- 薬効成分/効果効能: ビタミンK、ビタミンC、カルシウム、鉄分、カリウム / 止血、骨の健康維持、利尿、解熱作用
- 調理法の例: 若葉を茹でておひたし・和え物・汁物の具、粥の具、七草粥
- 採取できる場所: 道端、畑、庭
- 特徴と豆知識: アブラナ科の一年草で、春の七草の一つとしてよく知られています。白い小さな花と、扁平な逆三角形の果実が特徴です。果実の形が三味線のバチに似ていることから、「ペンペン草」や「シャミセングサ」とも呼ばれます。若葉はクセがなく、食べやすいので、様々な料理に利用できます。
ノビル

- 薬効成分/効果効能: アリシンなどの硫化アリル類、ビタミンC、ミネラル / 疲労回復、血行促進、殺菌効果
- 調理法の例: 葉や球根を刻んで薬味・和え物・汁物の具・炒め物・おひたし・天ぷら、醤油漬け、味噌漬け、酢味噌和え
- 採取できる場所: 土手、野原、日当たりの良い場所
- 特徴と豆知識: ユリ科の多年草で、ネギやニラのような香りが特徴です。地中に鱗茎(球根)を持ち、葉は細長い円筒状です。春になると、茎の先に紫色の小さな花が集まって咲きます。鱗茎や葉を傷つけると、ネギのような強い香りがします。「野蒜(のびる)」の名前は、野原に生えるヒル(ネギやニラなどのネギ属植物の古名)という意味です。鱗茎は生で食べると辛味が強いですが、加熱すると甘みが増します。ノビルは古くから食用とされていました。
ハコベ

- 薬効成分/効果効能: ビタミンC、ビタミンB群、カリウム、カルシウム、鉄分 / 代謝促進、利尿、消炎、止血作用
- 調理法・活用法の例: 若葉をサラダ、おひたし、和え物、天ぷら、汁物の具、ハコベご飯、塩を混ぜて歯磨き粉
- 採取できる場所: 庭、畑、道端
- 特徴と豆知識: ナデシコ科の一年草で、春の七草の一つです。白い小さな花が特徴で、花弁が深く5裂しているように見えますが、実際には10枚の花弁が深く切れ込んでいるためです。「ハコベ」の名前の由来は、茎が地を這う様子を「這い延(はこべ)」と表現したとする説や、葉を乾燥させて粉末にしたものを箱に入れて使ったことから「箱部(はこべ)」となったとする説などがあります。春の七草粥に入れるほか、柔らかい若葉はサラダやおひたしなどにして食べられます。昔は、ハコベをすり潰して、ハコベ風呂やハコベ湿布として利用したそうです。
ハハコグサ

- 薬効成分/効果効能: 食物繊維、ミネラル、フラボノイド / 便秘解消、抗酸化・抗炎症作用、咳止め、去痰作用
- 調理法の例: 若葉を茹でておひたし・和え物、草餅、お粥の具
- 採取できる場所: 道端、荒れ地、日当たりの良い場所
- 特徴と豆知識: キク科の越年草で、春の七草の一つ「御形(ごぎょう)」として知られています。白い綿毛に覆われた葉や茎が特徴で、触ると柔らかく、ビロードのような質感です。春に黄色い小さな花を球状に集めて咲かせます。名前の由来は、葉や茎が白い綿毛に覆われている様子を、母親が子供を包み込む姿に見立てたとする説などがあります。春の七草粥に入れる際、ハハコグサではなく、若い芽である「御形子(ごぎょうし)」を使う地域もあります。草餅の材料としても古くから利用されてきました。草餅にすると、独特の風味と香りが楽しめます。
ハルジオン

- 薬効成分/効果効能: ビタミンC、ミネラル / 抗酸化作用、利尿作用
- 調理法の例: 若葉をサラダ、おひたし、天ぷら、汁物の具
- 採取できる場所: 道端、空き地、公園
- 特徴と豆知識: キク科の越年草で、北アメリカ原産の帰化植物です。白い花弁と黄色い筒状花からなる花が特徴で、春から秋にかけて長く咲き続けます。よく似た野草にヒメジョオンがありますが、ハルジオンの方が花が大きく、茎が太く、つぼみがうなだれているなどの違いがあります。繁殖力が強く、道端や空き地など、どこにでも生育します。「ハルジオン」の名前は、春に咲く紫菀(しおん:キク科の植物)という意味です。
ホトケノザ

- 薬効成分/効果効能: ビタミンB群、ミネラル、食物繊維 / 整腸作用、代謝促進
- 調理法の例: 若葉をサラダ、おひたし、和え物、天ぷら
- 採取できる場所: 道端、畑、庭
- 特徴と豆知識: 春の七草の一つとして名前が挙がりますが、これは「コオニタビラコ」のことで、この「ホトケノザ」のことではありません。ピンク色の唇形の花が特徴で、葉が何段にも重なって茎を取り囲むように付きます。この葉の形が仏様の座る蓮華座に似ていることから「仏の座」と名付けられました。冬にロゼット状の葉で越冬し、春になると茎を伸ばして花を咲かせます。
ヨモギ

- 薬効成分/効果効能: β-カロテン、クロロフィル、食物繊維、精油成分 / 抗酸化作用、デトックス、リラックス、抗菌・抗炎症作用、便秘解消
- 調理法の例: 若葉を茹でておひたし・和え物・天ぷら、草餅、よもぎ団子、よもぎ湯、ハーブティー
- 採取できる場所: 土手、道端、荒れ地
- 特徴と豆知識: キク科の多年草で、日本各地に広く分布する代表的な野草の一つです。葉に独特の香気があり、触ると裏面が白い綿毛で覆われているのが特徴です。古くから食用、薬用、香料、灸(もぐさ)など、様々な用途で利用されてきました。草餅やよもぎ団子など、日本の伝統的な食文化に深く関わっています。「ヨモギ」の名前の由来は、「善萌(よもぎ)」、つまり良く萌え出ることや、良く燃える草であることから「燃草(もえくさ)」が転じたとする説などがあります。ヨモギは魔除けの力があると信じられ、端午の節句にヨモギを飾る風習があります。ヨモギ風呂は、体を温め、リラックス効果や冷え性改善効果が期待できます。ヨモギの葉を乾燥させて作る「もぐさ」は、お灸の材料として古くから利用されてきました。
注意点
- 食用や薬用にする場合は、しっかりと種類を特定し、信頼できる情報源で確認するようにしてください。
- 採取する際は、私有地や保護されている場所ではないかを確認し、許可なく採取しないようにしましょう。
- 体質によっては、野草が合わないこともあります。異常を感じたら使用を中止してください。(アレルギー)
- 触れただけで皮膚がかぶれたりする野草もあります。特に肌が弱い人は、注意しながら野草に触れるようにしましょう。
まだまだ解明し尽くされていない野草の力
身近な場所で摘むことができる春の野草たちをご紹介させていただきましたが、本当は今目につくすべての野草をご紹介したいくらいです!
また、紹介させていただいた効果効能や活用法も、ほんの一部だと思っていただけたらと思います。
「この野草には薬効はありません」
そう記された野草でも、不思議と驚くべき恩恵を与えてくれることがあります。
考えられる理由は二つあって、
①「薬効」が見つかっていないだけで、実は多くの薬効成分を含んでいる
②(物質的な)成分ではなく、野草の持つ何かしらエネルギーが作用した
このどちらかだと、個人的には考えています。
このような記事を書いておきながらなのですが、、、
私たちが調べられる野草の効果効能は、魅力の一つではあっても、それが全てではありません。
ネットや本で知ることができる効果効能だけに囚われず、もっと自然に、フラットに、野草と関わっていくことで、秘められた力に触れることができます。
調べてみると「薬効がない」とされている野草だったとしても、なぜかその野草がどうしても気になる時は、その野草があなたのことを必要としているサインかもしれません。
知識ではなく、意識で野草と関わっていく。
感性や本能を大切に、野草と触れ合っていかれてみてはいかがでしょうか?
最後までお読みくださりありがとうございました^^
<執筆・監修>
小釣はるよ(E&Wラボ 酵素と野草研究所 代表)
松・雑草発酵錬菌術師-どこにでもある「雑草」たちを、私たちの生命を輝かせる「宝物」に変える”錬金術”と”錬菌術”をお伝えしています。
★関連サイト
https://lit.link/haruyoeandwlabo
★著書
・野草を宝物に(ヒカルランド /2019年)
・野草マイスターのゆる魔女レシピ(ヒカルランド /2020年)
・[新装改訂版]野草を宝物に(ヒカルランド /2023年)
野草と発酵で人生を変える!
E&Wラボでは、今すぐ実践できる「野草と発酵生活のススメ」を学んでいただける、毎月2度の1DAYオンライン講座を開講しております。
▲いろんな健康法を試してきたけど、
どれも効果がイマイチで・・・
▲体だけでなく心の部分も癒していきたい
▲自然のリズムで日々を心地よく過ごしていきたい
という方には、
「野草と発酵を取り入れた究極のオーガニックライフ」が超おすすめです!
長年学んで来られた健康法の知識も活かしつつ、そこに野草と発酵の要素が加われば、これほど強いものはありません。
1DAYオンライン講座では、
「今オススメしたい旬の野草」
「秘められた野草の可能性や魅力」
「今の自分に必要な野草の選び方」
「潜在意識を癒す野草のメッセージ」
などをお伝えさせていただきます。
※定員がございますので、ピンと来たかたはお早めにお申し込みください。
年間オンラインスクール
E&Wラボでは、「野草と発酵ライフ」をオンライン上で学んでいただき、一年間で、それぞれの生活スタイルに合わせた「究極のオーガニックライフスタイル」を身に付けていただける、日本で唯一の「野草と発酵が学べるオンラインスクール」を運営しております。
▶︎▷▶︎ 年間オンラインスクールについて








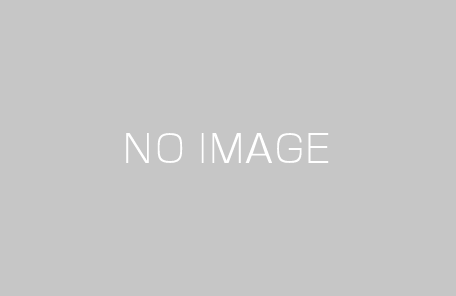
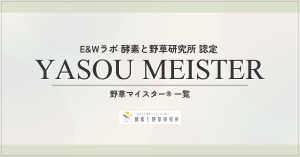



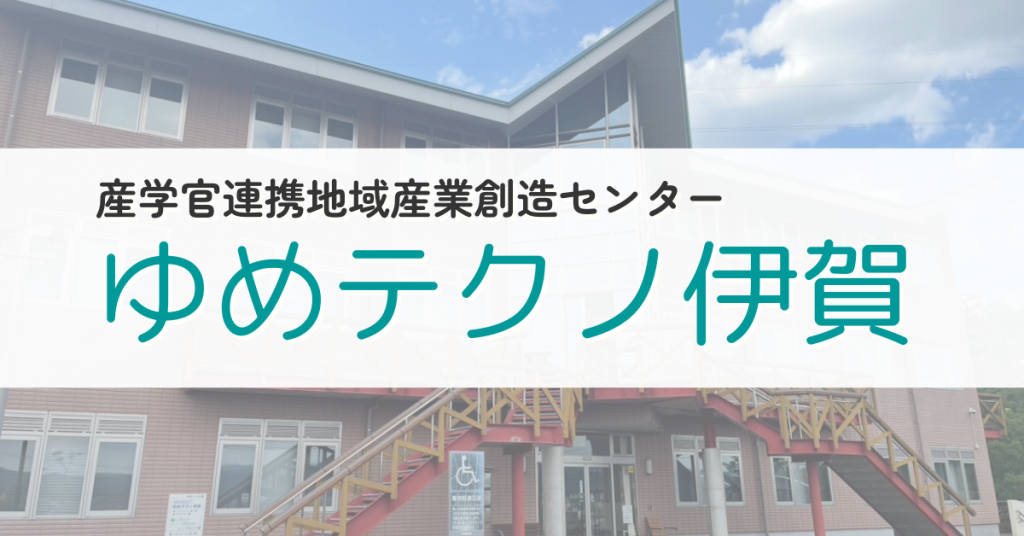

この記事へのコメントはありません。